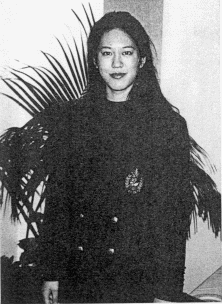
著者アイリス・チャンに聞く
なぜ私は「レイプ・オブ・南京」を書いたか
「論座」1998(平成10)年10月号より
まだ翻訳も出ていない一冊の書物が、日本でこれほど論じられたことがあっただろうか。
1997(平成9)年11月、当時29歳のジャーナリスト、アイリス・チャン氏が米国の出版社から出した「レイプ・オブ・南京―――忘れられた第二次大戦のホロコースト」をめぐって、一部の論壇誌や産経新聞に数多くの批判が書かれてきた。
早い時期の批判には、「南京事件」(中公新書)の著者である秦郁彦日本大学教授の「「南京虐殺」"証拠写真"を鑑定する」(諸君98年4月号)がある。
秦氏は、掲載写真に説明とまったく異なる状況の報道写真などが交じっていると指摘し、民間人の被虐殺数(26〜35万)や強姦被害者数(2〜8万)についても批判した。
続いて、文藝春秋北米総局長の塩谷紘氏が「外務省は「反日偽書」になぜ沈黙するのか」(「諸君!」5月号)を書き、米国の歴史学者らの批判的な見解を紹介した。
こうした米国での批判的見解は、産経新聞にも大きく取り上げられた。
代表的なものに、アメリカン大学名誉教授リチャード・フィン氏の「歴史より「反日主義」前面」(見出し)、ハーバード大学教授エズラ・ボーゲル氏の「中国側の情報うのみ、死傷者数根拠なし」(同)などある。
また、歴史教科書を「自虐史観に貫かれている」などと攻撃してきた藤岡信勝東大大学教授は、「新しい歴史教科書をつくる会」のシンポジウムで「レイプ・オブ・南京」を取り上げ、「ありとあらゆるデマが集大成されている」などと発言し、その記録は「正論」9月号に掲載された。
国際政治学者の浜田和幸氏の記事は、「アメリカを巻き込んだ中国のプロパガンダ工作に日本はなすすべもない目を覚ませ、ニッポン」の全文とともに「文藝春秋」9月号に掲載された。
波紋は論壇だけにとどまらない。
斉藤邦彦中米大使は4月21日の記者会見で同書に触れ、「非常に不正確で一方的な見解だ」などと発言した。
この発言に対しては、中国の駐米大使館が5月8日、「南京大虐殺は歴史的事実だ」などと反論した。
このように波紋が大きく広がっているのに、著者のアイリス・チャン氏の声は、日本にはほとんど届いていない。
「サンフランシスコ・クロニクル」のチャールズ・バレス記者が米国での反響と背景を詳細かつ客観的に報告した「アメリカを揺るがす「ザ・レイプ・オブ・南京」」(「中央公論」8月号)で一部が紹介された程度である。
本誌は、著者の声を伝えることが重要だと考え、在米ジャーナリストの徳留絹枝さんに、執筆のねらい、主要な批判についての質問を交えて、アイリス・チャン氏とのインタビューをお願いした。
以下は、一問一答と、斉藤駐米大使への質問書、大使への回答である。(編集部)
―――あなたの著書「レイプ・オブ・南京」について説明して下さい。
この本は、2つの、関連してはいるものの別個の、残虐行為を描いたものです。
1つは、日本軍が敵国の首都において何十万人もの市民を殺害した「南京のレイプ(虐殺)」と呼ばれる事件についてです。
もう1つは、中国とアメリカがこの事件に関して沈黙を続けてきたことに勇気づけられ、日本がこの虐殺の全容を人々の意識からかき消し、その過程で、この虐殺の犠牲者たちが占めるべき正当な歴史上の場所を奪ってきたという、隠蔽(いんぺい)についてです。
私の主張は、日本政府は少なくとも、被害者に対する正式な謝罪を表明し、この惨劇で人生を破壊された人々に補償をし、そして何よりも、この虐殺の事実を将来の世代の日本人に教えていくべきだというものです。
本をご覧になればわかると思いますが、ハーバード大学歴史学科長のウイリアム・カービー博士が大変好意的な前書きを、カリフォルニア大学のバークレー校東アジア研究所所長のフレデリック・ウェークマン、2人のピュリツアー賞作家(リチャード・ローズとデール・マハリッジ)、オックスフォード大学と著名な学者が、それぞれ推薦文を書いています。
この本は、この事件に関する研究に新境地を開いたことと質の高いリサーチが認められ、商業的成功と高い評価の両面をアメリカ国内で獲得しました。
国際的にもベストセラーとなり、これまで17刷を重ね、およそ13万部の売上を達成しています。
そしてニューヨーク・タイムズのノンフィクション新刊書部門のベストセラー・リストに5ヶ月間掲載されました。
過去数ヶ月の間に、この本は「ニューズウイーク」に抜粋紹介され、「ナイトライン」「グッドモーニング・アメリカ」「ジム・レーラー・ニュースアワー」などのテレビ番組、またピュリツアー賞受賞評論家ジョージ・ウィル氏のコラムを始め、ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、ウォールストリート・ジャーナル、ロサンゼルス・タイムズなどの一流紙、その他数多くのメディアで取り上げられました。
「ブックマン・レビュー」は、1997年度ベスト・ブックの1冊と指定しました。
―――それに比べると、あなたの本に関してこれまで日本で発表された記事は、大部分が否定的な内容なのですが、そのことをご存知ですか。ご存知だとしたら、それについてどう感じますか。
とくに驚いてはいません。
半世紀以上にわたって人々の意識からこの事件をかき消そうとしてきた日本国内の勢力について私が説明した、第10章を読んでもらえれば、その理由はわかると思います。
しかし、日本の右寄りのグループからの攻撃がこれほどすさまじいものであろうとは、そして日本国の大使までが、その地位を危険にさらしてまで私の本を攻撃してくるとは、予想していませんでした。
でも一方で、この本がこれほど攻撃を受けるのは、この本がいかに重要であるかの表れであると、多くの作者に言われました。
これらの攻撃は、日本に、この種の本が外国で出版されることに対する困惑があるということの表れだと思います。
もしこの本が本当にでたらめだというのなら、大騒ぎする必要などないからです。
―――この本を書くために2年を費やされたそうですが、なぜ南京大虐殺について書こうと思ったのですか。そしてそれは、どのような体験でしたか。
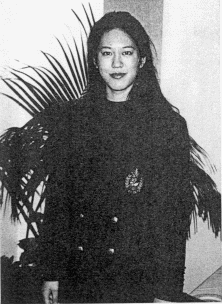 |
| アイリス・チャンイリノイ大学でジャーナリズムを専攻し、シカゴで短期間、記者として働いた後、ジョン・ホプキンス大学大学院でも学ぶ。著書に「蚕の糸(シルクワーム)」。 |
まだ小さかったころ、両親から聞かされる南京大虐殺の話に、私は身震いしたものでした。
日本軍が、中国の首都で何千人もの市民を虐殺し、子供まで残酷に殺したというのです。
それらの話は、私のなかで強烈な印象となって残りました。
その後、事件のことを調べようとしましたが、学校の図書館でも、市の図書館でも、世界史の教科書でも何一つ関連資料は見つけられませんでした。
もっとひどいことに、私の教師たちも、まったくこの事件のことを知らなかったのです。
ですから私にとって、この事件は長い年月、正確には94年に実際に虐殺の写真を見るまで、謎だったのです。
それでそれらの恐ろしい写真を見たとき、私は、このことを記録しなければならないと決心しました。
執筆は、本当につらい作業でした。
なぜなら、この本を書くために私は、多くの犠牲者がどれだけ苦しんだかを、自分の中で追体験しなければならなかったからです。
私の日常の生活まで影響を受けてしまわないように、私は、数々の残虐行為に関する情報を自分のなかで隔離することを、学ばなければなりませんでした。
それでも、この本を書いている間、私は本当に痩せてしまって、知人のなかには私を見分けられない人もいたほどです。
実際のリサーチとしては、15人の南京虐殺目撃者にビデオインタビューをし、4つの言語(中国語、日本語、ドイツ語、英語)にまたがる何千もの一級資料を
―――当時、"国際南京安全地帯"管理委員長でだったジョン・ラーベの日記も、発見されましたね。しかし、実際にその日記を発見したのはあなたではなかったと言う人物もいますが。
その人はいったい何を言っているのでしょう。
ラーベ家に直接問い合わせれば、誰にでもわかることではありませんか。
もちろん、私が洞窟の中で発見したと言っているわけではありません。
私がしたのは、長い間家族の間で保管されてきた日記を一般の人々に紹介したということです。
ラーベ家の人々は、この日記についてあまり語らないできましたから、私が彼らと連絡を取るまで、アメリカやヨーロッパの歴史家のほとんどは、その存在を知らずにいたのです。
ラーベ一家を探しだし、この日記を公表(エール大学に寄付)するよう説得したことにより、私は大きな貢献をしたと思っています。
―――あなたの本に関して指摘された具体的な批判について、1つずつお尋ねします。まず、収録された写真の信憑性を問題にする声があります。
私の本に収録されたすべての写真は、長い間パブリック・ドメイン(公の資料として誰でも使用できる状態)にあり、数々の書籍、博物館などで使用されてきたものです。
私の本に収録するにあたって、(注1)写真の修整やキャプションの変更などは、もちろんいっさい行われていません。
これらの写真が偽者だと主張する人々は、その重大な、時にはばかげた告発を裏づける(注2)証拠を提示していないのです。
ですからアメリカ人歴史家の多くは、これらの歴史修正主義者たちを、ユダヤ人ホロコーストやアルメニア人虐殺を否定する者たちと同じ範疇(はんちゅう)に入れています。
日本の歴史修正主義者たちは、私の本に収録された写真の1枚が、南京大虐殺以前に撮影されたと判明したことを指摘するのに、大変な時間を費やしているそうですね。
でも、その写真に添えられたキャプションをよく読めば、それがいつどこで撮影されたとは明記されていないことが、わかると思います。
ですから、厳密にはこの写真が偽物であると断言することは出来ないのです。
この写真は、(注3)日本軍が占領地域の女性たちを駆り集めた様子を捉(とら)えており、キャプションは、日本軍支配下に置かれた中国のそのような女性たちの多くに、集団レイプされ、日本軍の性的奴隷になることを強要されたのです。
―――虐殺の犠牲者数に疑問を呈する人々もいますが。
私の本には、犠牲者の数を論じた一章があります。
私は、そこで、これまでいろいろな人々によって主張されてきた主だった犠牲者数を列記しました。
東京裁判では、南京で26万人が殺されたという結論が出されましたが、それは低く見積もっての数と説明されています。
さらには(注4)大田寿男氏による、日本軍が15万体の死体を処理したという証言があります。
東京裁判の記録を読めば、証拠物件として提出された埋葬記録のあるものは、埋葬遺体数・埋葬日・男女の別などを詳細に報告していることがわかります。
誰でもアメリカの公文書館に出かけ、それらの資料を読むことができますし、法律大学院の図書館などにも、そのコピーは置いてあります。
―――犠牲者数をめぐる議論ばかりに追われると、この虐殺が実際に起こったということ、それがどのように起こったのか、なぜ起こったかという問題がおろそかになる懸念もあると思うのですが、犠牲者数を明かにすることは、どのくらい重要だと考えますか。
大規模な殺戮が行われた事実を確立することは重要なことだと思います。
(注5)もし3千人が殺されたというなら、歴史上最悪の殺戮の1つとは言えなくなります。
何より、人々は真実を知りたがるものです。
ですから、より正確な犠牲者数が判明するにこしたことはありません。
もちろん、犠牲者数に関していくら議論したところで、この殺戮の実態を私たちが忘れるわけではありません。
数の論議ではなく、人々がいかに殺されたかに焦点をあてるべきだと言う人もいるでしょう。
でも、南京虐殺は起きていなかったと主張する歴史修正主義者がいると思うとき、私はどちらの側面も重要だと考えます。
―――デビット・バーガミニの「日本皇室の陰謀」を資料として用いたことに対する批判には、どう答えますか。
私はこの本のなかで、上層部の誰に虐殺の責任があったかを究明することは非常に困難であると、書きました。
その主な理由は、この件に関する一級資料を見つけることが著しく困難だからです。
その理由の1つは、アメリカが戦後押収した資料の多くを、マイクロフィルム化しないまま日本に返還してしまったことにあります。
さらには、戦後、当時の状況に関して証言させられた南京入城時の日本軍将官たちの言葉が真実を語っているのか、何かの圧力で虚偽の証言をしているのか、判断できないという問題があります。
それで私がこの本でしたことは、一級資料を得ることの困難さを明確にしたうえで、なぜそれらの資料を得ることが難しいのかを説明し、それではどのような記録や議論が存在するのかということを、読者に伝えることでした。
ある種の資料は完全に信用できないかもしれないし、欠損個所がある記録もあるでしょう。
でも、長い年月の間でこれらのものが私たちの手元に振るい落とされてきたということです。
私には、少なくとも、これらの資料が活字として存在することを読者に知らせる責任があるのです。
もし日本政府が、南京虐殺に関する一級資料をもっと見たいというのなら、(注6)彼らが保管している文章を公開すればいいのです。
| ホームページ作者による注記における解説 | ||
| (注1) | ・・・ | アイリス・チャン著作「THE RAPE OF NANKING」掲載写真の数枚はトリミング、もしくは意図的に写真の改ざんもしくは資料誤用が確認されている。別項参照。 |
| (注2) | ・・・ | 証拠、根拠はすべて提示されています。 |
| (注3) | ・・・ | 別項参照 |
| (注4) | ・・・ | 「太田壽男供述書」は戦後撫順戦犯管理所(洗脳教育を行っていた収容所)に戦犯として監禁収容されていた際に提出した罪行供述書であり現在ではどの研究者も信憑性無しとしている。 |
| (注5) | ・・・ | 南京金陵大学社会学科ルイス・S・C・スマイス教授は戦後南京戦における一般人の被害について調査を行い、南京市内外における被害者総数は2400人という結果を発表している。 |
| (注6) | ・・・ | 南京戦における一級資料のほとんどは発表されており映像資料も数多く存在している。偕行社「南京戦史」、スマイス博士著「南京地区における戦争被害」もそれに当たる。 |