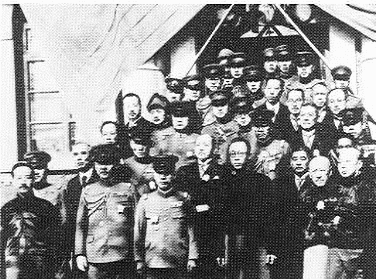 |
3、煽(あお)られた中国の反日ナショナリズム
形成される反日包囲網
ところで、第1次大戦は、列強の世界的地位の大きな変動をもたらしていた。
満州の権益についてわが国と共通の利害に立っていたロシアは、大戦中に革命によって倒れてしまった。
世界一の大帝国であった英国も、大戦によって疲弊し、米国の援助によって戦後再建を果たさなければならなくなったからである。
いわば今日のパクス・アメリカーナ、すなわち世界政治の主導権を米国が握る時代の端緒となったのである。
その米国政策の基本は、日本と中国との条約、また日英・日露の協調関係という安定要因を1つ1つ切り崩し、反日包囲網を形成していくことにあった。
米国は、ワシントン会議において日英同盟を英国に圧力をかけて解体させ、次いで日本と条約を結んでいた中国の北京政府ではなく国民党政府を支援して、日支条約の否認、日本の満州権益の即時回収を叫ばせた。
一方、ロシア革命によって成立したソ連に対しても、米国はイデオロギー的には不仲であったにもかかわらず、米ソ協調路線をとり、日本の満州権益をめぐる反日包囲網を組み入れていったのである。
後に行われたABCD包囲網による経済圧迫こそが、わが国の大東亜戦争開戦決意の導火線とされているが、実は、以前から米国を中心として中国より日本を追放するための反日包囲網が順次形成されていたのである。
中国の反日ナショナリズム
満州奪取の目的のため、その中でも米国が最も力を尽くしたのが、中国の反日感情を利用することであった。
それゆえ米国は、一貫して中国の反日ナショナリズムの煽動、育成に努めていたのである。
すなわち21箇条条約交渉の課程においては、中国側当局者以上に米国の駐中国公使ライシュ自身が、外交官としての範囲を逸脱した激しい反日活動を行っている。
更に第1次大戦後には、米国は、日本が実質上得ていたドイツ領の青島を日本が継承することに反発して返還を求めた中国側を支援している。
そして日本をして青島の中国返還を余儀なくさせたが、これも中国への同情より日本の勢力拡大阻止に米国の狙いはあったのである。
ワシントン会議などで米国自身が対日強硬姿勢を貫いたことは、中国側に米国の好意的な後ろだてがあるという自信を与えた。
それは結果的に、中国における反日運動を煽ることとなったのである。
当時、中国全土の状況は「人民の権利が守られている地方は皆無であり、人民は重税にあえぎ、生命と財産は不安にさらされ、盗賊は全国的、飢餓は一般的であった」(アメリカ陸軍のスチルウェル少佐の報告)。
その中で満州を中国全土で一番の治安状態に保ち、経済的にも発展させていたのは日本の努力による。
その日本が、不当な中国側の回収要求をはねつけるのは当然のことである。
しかしながら、米国が日本勢力の駆逐を宣伝する蒋介石と張学良との反日提携を仲介した結果、中国の国会では「租界回収・関東軍撤退」が絶叫され、米国の支持を頼んで日本側の外交的手段による解決の試みを受け付けようとはしなかった。
その上で中国側は日本人居留民に対する暴行、示威という暴力的手段すら用いていった。
日本人経営の商店で買い物した客から取引税を改めてとったり、日本人に土地家屋を貸した満人を投獄したり、更には長春や奉天では巡警自ら日本人と見ると袋叩きにしたり投石するといった事件が頻発し、小学生の通学を領事館警察隊が護衛するという異常な状態が日常化したのである。
朝鮮人農民に至っては、入植した農地を取り上げられ、暴行を受けた上で家財道具一切を略奪されて追放されていった。
こうして20万にも昇る日本人が餓死か日本への引き上げかを決断するところまで追いつめられていった。
それゆえ、日本の新聞では「在満日本人の苦難の真犯人はアメリカ資本である」との論が掲載されるようになったのである。
南満州鉄道及び旅順は日本にとって対ソ防衛のための生命線とされる重要地帯でありまた日本の正当な権益である。
ところが今や米国を後ろ盾とする中国側の不当な行動によって転覆の危機に瀕していた。
このような情勢下、危機に瀕した満州権益を防衛するために、ついに駐屯軍である関東軍が軍事行動を起こした。
これが満州事変であった。
明治以来、満州の安危はわが国の安全に直結するものとして考えられてきた。
しかし列国は、中国政情の混乱を利用して様々な介入を図ってきた。
ことに国民党と結んだソ連による様々な策動によって満州事変を余儀なくされたのである。
そこで米ソの策動を押さえ、かつ混乱した中国本土の政争を満州に持ち込ませないための抜本解決手段とされたのが満州建国であった。
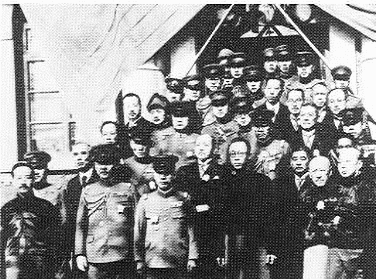 |
阻害された日中和平への道
当然、米国は満州国建国をあくまで認めようとはしなかった。
国際的地位を飛躍的に向上させていた米国の意向は、列強も無視し得ず、国際連盟が派遣したリットン調査団は、満州における日本の権益を認め、日中間において満州に関する新しい条約の締結を勧告するなど日本の立場を認めたものの、満州国建国を日本による侵略行為であるとして非難した。
この国連の実態に対して国民世論は激高し、国連即時脱退論が大勢を占め、ついにわが国政府は、国連脱退を決定したのである。
ところで、満州国の建国という新しい事態を受けての、新しい日中間の関係は安定しないままに終わった。
日中間に和平のチャンスがなかったわけではない。
わが国が日中和平を切望し、しかも幾多の真剣な和平交渉が行われたのは歴史的事実である。
にもかかわらず、それは実を結ばなかった。
失敗の大きな理由の1つには、米国自信が、日中の早期和平を望まなかったことが挙げられる。
米国は、建前としては日中の早期和平を要求していたが、本音では日本がアジアにおいて軍事的に卓越した立場に立つことをよしとしなかったからである。
すなわち、中国における日本の立場が強化され、満州の権益が安定することを恐れたからである。
それゆえ米国は、一貫して強い反日姿勢を示し、和平よりも日中の戦乱継続を望んで、中国側の強硬姿勢を後押しし続けた。
そうした米国の日中和平の阻害意図は、例えば、昭和14(1939)年7月の日米通商航海条約廃棄通告にも明らかである。
折から日英両国では、英国側による満州国承認など日本にとって融和的で内容で中国問題での妥協が成立しかけていた。
そこに出されたのが米国の日米通商航海条約廃棄通告であった。
この米国の強行姿勢によって英国側は態度を一変させて交渉は決裂に終わった。
蒋介石は、米国側の行動を高く評価し「今回の措置は、中国の危機を救うに大に役立った」と発言し日中戦争継続の意志を更に固めたのである。
米国の基本姿勢は、ハル米国務長官の「中国が勝利しなければ、いかなる調停工作も、軍事力によって獲得された政治的、領土的利益に関して日本の合法性を認める結果をもたらすので、アメリカ政府は中国紛争終結の努力をすべきでない」という発言からも明瞭である。
米国の意図がこのようなものであるかぎり、米国の援助にその政権維持を全面的に依拠している蒋政権が対日和平に動くはずはなかった。
 |
次のページへ |